COLUMNコラム
CATEGORY
-

【NEAR科学】③日常に取り入れるコツ!対話で育む心と脳の健康
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 子どもと良好な関係を築くためには、どういったことが必要でしょうか? 子どもの声を聴くことの大切さにもつながるものであり、その鍵となるのが、「対話」と「尊重」です。 子どもが安心して成長できる環境を整えるために、NEAR科学では、「安全」「つながり」「回復」を基盤とする関わりが重要であるとされています。これらの要素がしっかりと整えられた環境では、子どもは自…続きを読む
-

【NEAR科学】➀NEAR科学って何?『心と脳の仕組み』をひも解く新しい視点
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 新しい年が明け、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 昨年も多くの方々に支えられ、無事に一年を過ごすことができましたこと、心より感謝申し上げます。 本年も、皆さまの日々の生活やお仕事に少しでも役立つ情報をお届けできるよう努めてまいります。コラムを通じて、より多くの気づきや学びを共有できれば幸いです。 皆さまにとって、この一年が希望に満ちた素晴らしい年となりま…続きを読む
-

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】④子どもの意見表明を阻む課題と向き合うために
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 2024年も終わりに近づき、日々の忙しさの中でふと立ち止まり、この一年を振り返る季節となりました。皆さまにとって、どのような一年だったでしょうか? コラムのテーマとして掲げてきた「子どもとの心の向き合い方」。それは、子どもたち一人ひとりの声に耳を傾け、その心の奥にある気持ちを丁寧に汲み取ることの大切さを改めて実感した一年でもありました。子どもたちが抱える…続きを読む
-
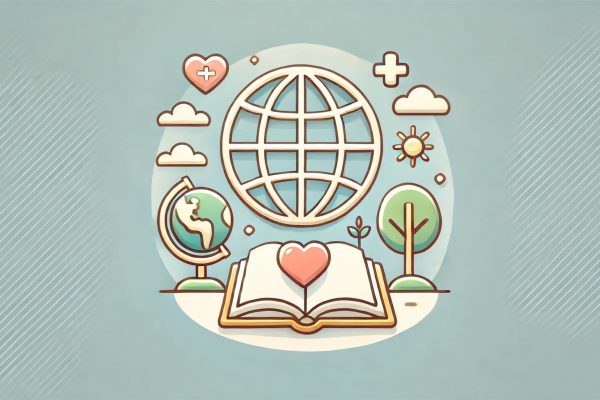
【こどもの声を尊重する新しい仕組み】③子どもの権利条約を基盤とした海外の取り組み
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 現代社会において、子どもたちの声を聴くことが、私たち大人の重要な役割であることが改めて注目されています。子どもは、日々の生活の中でさまざまな思いや意見を持っていますが、それを伝える機会や方法が限られていることが多いのも現実です。そこで、「意見表明権」という概念が世界的に取り上げられ、子どもたちが自身の言葉で自らの意見や感情を表現できる権利が重視され始めて…続きを読む
-

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】②意見表明等支援員の役割と意義
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 前回からのコラムでこどもアドボケイトに関する話題を紹介していますが、テーマの中心であるこどもの声を尊重する新しい仕組みの昨今の動きについてざっと紹介したいと思います。虐待を理由に一時保護されたこどもの声を代弁する「意見表明等支援員」の配置事業が、今年度に児童相談所を設置している79自治体のうち約8割の自治体で実施されています。これは、こどもの意見表明権を…続きを読む
-

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】①こどもの意見聴取等措置の意義
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 今回のテーマである「こどもの意見聴取等措置」は、子どもの権利を尊重し、こどもの声を社会や福祉・教育現場において積極的に取り入れることの重要性を強調するものです。今回のコラムのテーマをとりあげようとした背景には、まず第一に、こどもの意見を聴取することがこどもの自己肯定感や主体性の育成に不可欠であるという認識があります。また、こどもの権利条約に基づき、福祉や…続きを読む
-

【子どもの貧困問題への取り組みを考える】②子どもの貧困への対応
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 今年のゴールデンウィークは、気持ちの持ちよう的には、コロナ禍前とどこか同じ気持ちになる人が大勢いるのではないでしょうか。それを表す一つの動きとして、大型連休中に国内旅行をする人がコロナ禍以前の2019年と同じ水準まで回復するという見通しを旅行会社がまとめました。また新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて、政府は2023年5月8日に、季節性インフ…続きを読む
-

【子どもの貧困問題への取り組みを考える】①現代社会における貧困とは?
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 コラムでも取り上げました「こども家庭庁」が発足されて、早1ヶ月が経とうとしています。日常で何かがすぐに変わることはないとは思いますが、昨今の子どもの自殺の増加に対して、こども家庭庁がそうした状況を鑑みて、自殺対策室を設置しました。警察庁、文部科学省、厚生労働省と連携し、子どもの心のケアに対しての体制作りの強化を迅速に図る動きから、こどもまんなか社会を目指…続きを読む
-

【こどもまんなか社会を目指す】④子ども基本法とは・・・
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 前回は、こども家庭庁の体制についてお伝えしました。3つの部門からなる体制のもとで、こども家庭庁は子どもへの支援を充実させていこうとしています。加えて5年をめどに組織や体制のあり方を再検討して、必要に応じて見直すことなどについてお伝えしました。詳しくはこちらをご覧ください。 【こどもまんなか社会を目指す】③こども家庭庁の体制 そして、いよいよこども家庭庁が…続きを読む
-

【こどもまんなか社会を目指す】③こども家庭庁の体制
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 冬のような厳しい寒さは少なくなったものの寒くなったり、春の陽気になったり、三寒四温とはまさにこのことだなと感じる日々です。4月まではあと少しとなり、出会いや別れの季節とともに、新年度を向かえて新たな気持ちで臨んでいこうとする区切りの時期でもあります。次年度も気持ち新たにいろいろなことへ挑戦していきたいものです。 さて2月のコラムでは、こども家庭庁が取り組…続きを読む
-

【こどもまんなか社会を目指す】②こども政策とこども家庭庁が大切にする3つの姿勢
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 前回は、「こどもまんなか社会」を目指すために設置された、こども家庭庁の成り立ちや役割についてお伝えしました。今回はこどもに関連する政策や、こども家庭庁が大切にする姿勢について一緒に考えていきたいと思います。 前回のコラムはこちらからご覧になれます。 【こどもまんなか社会を目指す】①こども家庭庁の成り立ちと役割 【こども政策で大切にすること】…続きを読む
-

【こどもまんなか社会を目指す】①こども家庭庁の成り立ちと役割
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 早速ですが、「人新世」という言葉を聞いたことがありますか?私は最近知ったのですが、読み方すら分からず、某アニメの新作なのかと思ったくらいです。調べてみると・・・今を生きる我々にとても関係している言葉でした。 21世紀以降を「人新世(じんしんせい、ひとしんせい)」という時代区分として捉えようと提唱されています。この「人新世」という言葉は、人類が地球の生物圏…続きを読む
-

【子どもアドボカシー】話をしても良いという安心感
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 日本には春と夏の季節の合間に梅雨があります。じめじめして、蒸し暑くなんとも言えない時期です。私はこの時期があまり好きではありません。晴れる日も少なく、なかなか気分が晴れやかになることもなく、気持ちもどんより。ただ最近は梅雨の時期を楽しもうとも思っています。ここ数年のコロナ禍で、逆境に負けない気持ちが知らず知らずのうちに身についてしまったのかもしれません。…続きを読む
-

【児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)】ひとりの人間としての権利を考える
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 3年ぶりとなる行動制限のないゴールデンウイークが明けて、しばらく経ちましたがいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウイーク中の各地ではコロナがなかった頃の賑わいを取り戻し、そうした風景を目にし、どこかほっと一安心しました。 ゴールデンウイーク期間中の祝日である「こどもの日」は1948年に「子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」お…続きを読む
-

【日本におけるヤングケアラーの現状】ケアを担う子どもたち
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 新年度が始まり早半月となりました。このコラムでは子どもの心との向き合い方をさまざまな視点で考えていきます。2022年の4月1日から子どもが18歳で成人となる大きなニュースが話題となりました。親の同意なしで出来ることも増える一方で大人としての責任も課せられる場面が起こり得ることでさまざまな心配事もあるとは思います。そうしたことも乗り越えて頑張ってもらいたい…続きを読む
