COLUMNコラム
CATEGORY
-

【折れない心を育む】心理士(師)が伝える:安全基地って何?「子どもにとっての家庭・家族の役割」<親子でできるワーク付>-part4-
所属カウンセラーの水野です。 皆さまには、清々しく新しい年をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い致します。 年末年始は、昨年の疲れを癒し、少しゆっくりとお過ごしいただけましたでしょうか。 仕事や学校が始まり、日常へと戻られる時期かと思いますが、急に頑張りすぎず、心や身体を少しずつ慣らしながら、ご自身のペースで日常に戻っていただけたらと思います。 現在、私のコラムでは…続きを読む
-

【折れない心を育む】心理士(師)が伝える:「子どもに体験させたい3つのこと」<親子でできるワーク付> – part3 –
所属カウンセラーの水野です。 12月になりました。 空気がすっかり冷たくなり、吐く息が白くひろがる季節になりました。 皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 気温がぐっと下がるこの時期、そして次の年を迎えるにあたって慌ただしくなるこの時期は、大人も子どもも、いつもより少し心が敏感になります。 「なんとなく落ち込みやすい」「疲れが抜けにくい」 そんな感覚を覚えている方もいらっしゃるかもしれません。 寒さ…続きを読む
-

【折れない心を育む|番外編】「秋バテ対策」で寒い冬に“心を備えよう”!-喪失と再生の狭間で-<親子でできるセルフケア付>
所属カウンセラーの水野です。 11月になり、とても寒い日々が続いています。 今年はまるで秋を飛び越えて、いきなり冬がやってきたような気候ですね。皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 私は脚に金属を入れていることもあってか、10月中旬にグッと気温が下がった頃から、急に「内側から沁みいる冷たさ」を感じるようになりました。まさに「身に沁みる」という言葉そのものです。季節や気温が、これほどまでに身体に影響を…続きを読む
-

【折れない心を育む】心理士(師)が伝える:「自分の心のキャパシティを守る大切さ」〜 子育て相談をお受けする時の視点-part2 –
所属カウンセラーの水野です。 10月になり、夏本番よりは涼しくなったかと思いますが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 涼しくなることは、過ごしやすくて嬉しい一方で、疲れも出やすい時期でもあります。しっかりとした休息、心の安らぐ時間を持って、今から冬の寒さに備えていきたいですね。 そして、来たる来週の月曜日10月6日は「中秋の名月」だそうです。 お恥ずかしい話なのですが、「中秋の名月」は、9月中に…続きを読む
-

【折れない心を育む】心理士(師)が伝える:「子育てで大切なこと」〜 子育て相談をお受けする時の視点-part1 –
所属カウンセラーの水野です。 ご無沙汰しております。 夏休みが終わり、新学期が始まりましたが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 まだまだ暑さは続きますが、しっかりとした水分補給、心の安らぐ時間を持ちながら、生き延びてまいりましょう! 術後の療養につき、長らくコラムを更新できずにおりましたが、またこのように皆さまにお会いできて、とても嬉しく思います!! 今後も不定期になるかと思われますが、皆さまの…続きを読む
-

【NEAR科学】③日常に取り入れるコツ!対話で育む心と脳の健康
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 子どもと良好な関係を築くためには、どういったことが必要でしょうか? 子どもの声を聴くことの大切さにもつながるものであり、その鍵となるのが、「対話」と「尊重」です。 子どもが安心して成長できる環境を整えるために、NEAR科学では、「安全」「つながり」「回復」を基盤とする関わりが重要であるとされています。これらの要素がしっかりと整えられた環境では、子どもは自…続きを読む
-
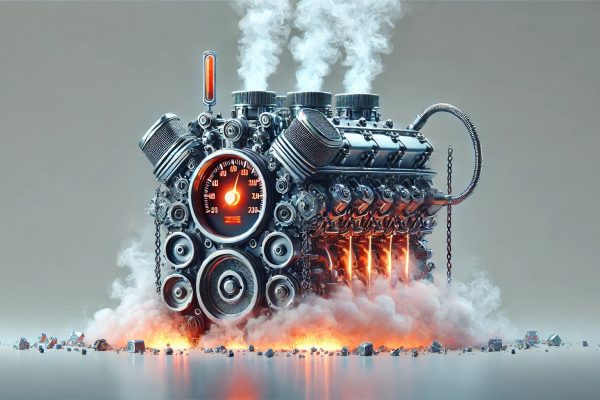
【NEAR科学】②ストレスでエンジンがオーバーヒート!? ストレスに強い脳と心をつくるためにできること
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 2000年代初頭、「遺伝子は運命を決める」という従来の考え方に新たな光を当てる研究が登場しました。それが「エピジェネティクス」という分野です。この研究によって、遺伝子は単なる設計図ではなく、環境や経験によってその働きが調整され、変化することが明らかになってきました。特に、ストレスやトラウマが遺伝子の発現に影響を及ぼし、その影響が次世代にも受け継がれる可能…続きを読む
-

【NEAR科学】➀NEAR科学って何?『心と脳の仕組み』をひも解く新しい視点
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 新しい年が明け、皆さまいかがお過ごしでしょうか。 昨年も多くの方々に支えられ、無事に一年を過ごすことができましたこと、心より感謝申し上げます。 本年も、皆さまの日々の生活やお仕事に少しでも役立つ情報をお届けできるよう努めてまいります。コラムを通じて、より多くの気づきや学びを共有できれば幸いです。 皆さまにとって、この一年が希望に満ちた素晴らしい年となりま…続きを読む
-

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】④子どもの意見表明を阻む課題と向き合うために
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 2024年も終わりに近づき、日々の忙しさの中でふと立ち止まり、この一年を振り返る季節となりました。皆さまにとって、どのような一年だったでしょうか? コラムのテーマとして掲げてきた「子どもとの心の向き合い方」。それは、子どもたち一人ひとりの声に耳を傾け、その心の奥にある気持ちを丁寧に汲み取ることの大切さを改めて実感した一年でもありました。子どもたちが抱える…続きを読む
-
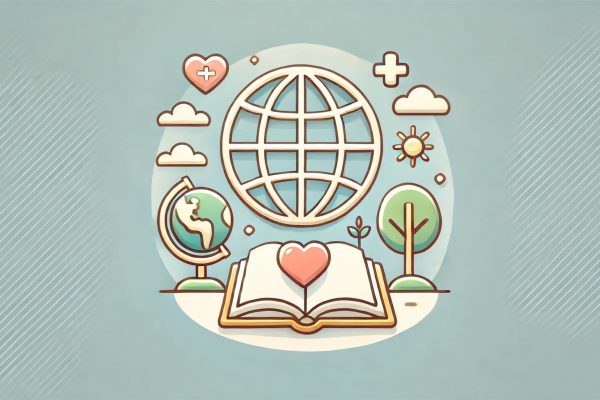
【こどもの声を尊重する新しい仕組み】③子どもの権利条約を基盤とした海外の取り組み
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 現代社会において、子どもたちの声を聴くことが、私たち大人の重要な役割であることが改めて注目されています。子どもは、日々の生活の中でさまざまな思いや意見を持っていますが、それを伝える機会や方法が限られていることが多いのも現実です。そこで、「意見表明権」という概念が世界的に取り上げられ、子どもたちが自身の言葉で自らの意見や感情を表現できる権利が重視され始めて…続きを読む
-

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】②意見表明等支援員の役割と意義
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 前回からのコラムでこどもアドボケイトに関する話題を紹介していますが、テーマの中心であるこどもの声を尊重する新しい仕組みの昨今の動きについてざっと紹介したいと思います。虐待を理由に一時保護されたこどもの声を代弁する「意見表明等支援員」の配置事業が、今年度に児童相談所を設置している79自治体のうち約8割の自治体で実施されています。これは、こどもの意見表明権を…続きを読む
-

【こどもの声を尊重する新しい仕組み】①こどもの意見聴取等措置の意義
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 今回のテーマである「こどもの意見聴取等措置」は、子どもの権利を尊重し、こどもの声を社会や福祉・教育現場において積極的に取り入れることの重要性を強調するものです。今回のコラムのテーマをとりあげようとした背景には、まず第一に、こどもの意見を聴取することがこどもの自己肯定感や主体性の育成に不可欠であるという認識があります。また、こどもの権利条約に基づき、福祉や…続きを読む
-

【トラウマインフォームドケアという関わり】⑧実践するための4つのR(後編)
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 これまでの連載で「トラウマインフォームドケア(TIC)」について、お伝えしてきました。今回のコラムでシリーズの最終回となります。前回のコラムではTICが、トラウマを抱える人々への効果的な支援を目指し、理解(Realize)、認識(Recognize)、対応(Respond)、再トラウマ体験を防ぐ(Resist re-traumatization)という4…続きを読む
-

【トラウマインフォームドケアという関わり】⑦実践するための4つのR(前編)
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 「生きづらさ」という言葉を耳にすることがあります。この言葉の背景にはその時代におけるさまざまな要因によるものが「生きづらさ」の原因になっていると考えることができます。ただし、根本にあるものとして幼少期の逆境体験、いわゆるトラウマがその大きな要因になっているのではないかと、さまざまなトラウマに関する研究で明らかにされつつあります。トラウマに関してかなりのこ…続きを読む
-

【トラウマインフォームドケアという関わり】⑥トラウマインフォームドケアの原則
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 今回のコラムでは、皆様とご一緒に重要なテーマについて考えていきたいと思います。トラウマインフォームドケアについてです。トラウマとは、私たちの心に深い傷を残すことがあります。そして、その傷は時に癒えにくく、私たちの日常生活に影響を与えることもあります。 しかし、幸いなことに、トラウマに対する正しいサポートとアプローチがあることを知っていますか?それがトラウ…続きを読む
-

【トラウマインフォームドケアという関わり】⑤子どものトラウマ反応について
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 最近、日本での共同親権の導入について注目しています。現行制度では、離婚後の親権は父親か母親の一方が持つ「単独親権」ですが、「共同親権」導入となれば、両親が合意すれば共同で子育てをすることが可能になります。合意が難しい場合は家庭裁判所が判断することになり、家庭内暴力などの懸念がある場合は単独親権が選択されることになる可能性があります。 一般的に、共同親権は…続きを読む
-

【トラウマインフォームドケアという関わり】④こころのケガになりうる出来事
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 この記事を書いている頃、東京に久しぶりの雪が舞い降り、街の景色は一変しました。冷たい風が鼻先をかすめ、空気中には雪の粉が舞い踊っていました。職場の一つである児童養護施設では、子どもたちが喜び勇んで庭や公園で雪合戦を楽しんでいました。その無邪気な笑顔が、私のこころにほんのりと温かさをもたらしてくれました。雪の中で純粋に楽しむ子どもたちのように、私たちも心の…続きを読む
-

【子どものこころとの向き合い方】家族とのコミュニケーション
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 新たな新年を迎えましたが、能登半島地震という心痛む1年の幕開けとなりました。 この度の能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 これ以上被害が広がらないこと、被災地域の一日も早い復興を心からお祈りしております。 新年が始まり、新たな一歩を踏み出す季節がやってきました。そのため今回のコラムですが、前回まで扱っていた「トラウマ…続きを読む
-
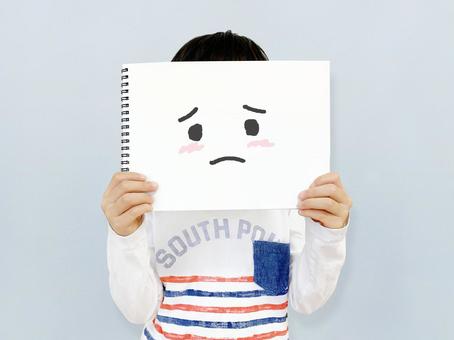
【トラウマインフォームドケアという関わり】③子どもの気になる行動の背景を理解するためのヒント
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 ここ数年、秋らしさが短くなったように感じるのは私だけでしょうか。秋らしからぬ暑さが続くため、紅葉の時期もズレたりと、季節らしさを楽しむ瞬間を今まで以上に意識しないと四季の良さを見過ごしてしまいそうです。 さて今年からこども家庭庁が設けた「秋のこどもまんなか月間」では、子どもや子育て家庭を社会全体で支援する動きをさらに盛り上げるための取り組みが行われていま…続きを読む
-

【トラウマインフォームドケアという関わり】②なぜ今の時代に必要とされているアプローチなのか
こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。 気が早いのですが、来月11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」となっています。平成16年度から令和4年度まで厚生労働省において「児童虐待防止推進月間」として実施されていました児童虐待防止キャンペーンが、実は令和5年度からは、こども家庭庁が取り組むことになりました。「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」として、家庭や学校、地域等の…続きを読む
