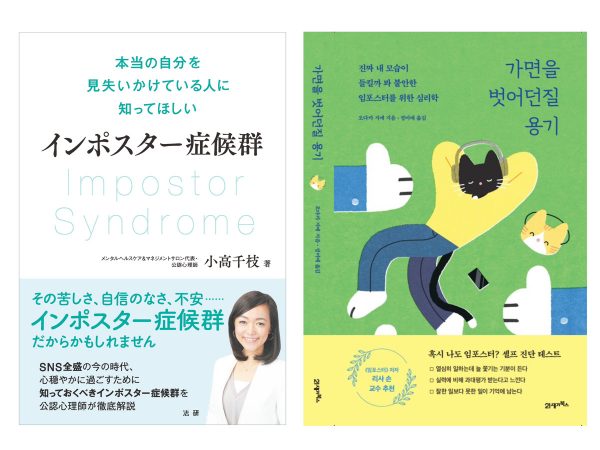こんにちは、所属カウンセラーの古宇田です。
新しい年が明け、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
昨年も多くの方々に支えられ、無事に一年を過ごすことができましたこと、心より感謝申し上げます。
本年も、皆さまの日々の生活やお仕事に少しでも役立つ情報をお届けできるよう努めてまいります。コラムを通じて、より多くの気づきや学びを共有できれば幸いです。
皆さまにとって、この一年が希望に満ちた素晴らしい年となりますよう、お祈り申し上げます。
どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。

さて前回のコラムでは、【こどもの声を尊重する新しい仕組み】④子どもの意見表明を阻む課題と向き合うためにをお伝えしました。日本で子どもの意見が十分に尊重されていない現状についてお伝えしました。子どもを一人の個人として意見を大切にすることの重要性を強調しました。また、大人が子どもの声に耳を傾ける姿勢を持ち、信頼関係を築くためのスキルを身につける必要性についても触れました。さらに、子どもの意見を具体的な行動や計画に反映させることで、子ども自身が自分の意見が尊重されていると感じられる環境づくりの大切さを考えました。前回コラムはこちらからご覧になれます。
【こどもの声を尊重する新しい仕組み】④子どもの意見表明を阻む課題と向き合うために
今回は、あまり聞きなれないテーマになるかもしれませんが、今までのコラムでもいくつか紹介してきたテーマが含まれるものになっています。今回のテーマは「NEAR科学」についてです。「ストレスやトラウマが脳や心にどんな影響を与えるのか?」――その答えを探るNEAR科学は、現代の悩みを解決する新たな鍵です。心身の健康を守り、困難を乗り越える力を育むこのアプローチは、ストレス社会を生きる私たちに新しい希望をもたらすことが期待されています。
【ストレス社会に生きる私たち】

「最近なんだか疲れやすい」「イライラが止まらない」――そんな経験はありませんか?
現代社会において、私たちは日々、多様なストレスにさらされています。仕事や家庭、学校でのプレッシャーに加え、SNSやメディアから流れる大量の情報が心の負担となっています。これにより、不安や過労など、心身の不調を訴える人が増えています。これらのストレスは、単に気分や体調を悪くするだけでなく、私たちの“脳”にまで深刻な影響を及ぼします。
この状況下で、「心の健康をいかに守るか」という課題は、社会全体で解決すべき重要なテーマとなっています。そんな中、注目を集めているのが脳と心の仕組みを、ストレスやトラウマの視点から解き明かす「NEAR科学」というアプローチです。
【NEAR科学とは?】

NEAR科学とは、「Neuroscience, Epigenetics, ACE(Adverse Childhood Experiences), Resilience」の略で、「脳科学」「エピジェネティクス(後成遺伝学)」「ACE:小児期の逆境体験(※1)」「レジリエンス(回復力)(※2)」といったテーマを包含しています。
このアプローチは、トラウマや慢性的なストレスが脳や体にどのような影響を及ぼすかを解明し、その結果を基に個々人に適した支援や環境の構築を目指します。つまり「脳と環境の関係を理解し、心と体が健やかに回復する方法を考える科学」ということになります。これにより、人々が困難を乗り越え、より健康で豊かな生活を送れるようにすることが目的です
【ストレスが脳に与える影響】

ストレスが脳に与える影響は計り知れません。NEAR科学によれば、長期間のストレスは脳の構造や機能に深刻な変化を引き起こします。例えば、危険や恐怖を感じる役割を担う扁桃体が過活動になることで、常に緊張状態に陥ります。また、理性的な判断や計画、感情のコントロールを担う前頭前野の機能が低下し、日常生活に支障をきたす場合があります。さらに、記憶や学習能力を司る海馬が縮小することで、記憶力やストレスへの抵抗力が低下してしまいます。
これらの脳の変化は、子どもだけでなく大人にも影響を及ぼします。しかし、NEAR科学では、こうした変化を理解し、適切な介入を行うことで脳の回復を促進できると考えています。私たちは脳の健康を守るために、ストレスケアを意識的に生活に取り入れる必要があります。
【トラウマとエピジェネティクス】

近年、子どもたちのストレスやトラウマが社会問題になっています。これを放置すると、大人になってからの健康や人間関係に影響が出ることがわかっています。NEAR科学は、子どもたちの未来を守るための重要なアプローチでもあるのです。
最新の研究では、トラウマが遺伝子レベルでどのように影響を及ぼすかが注目されています。エピジェネティクス(後成遺伝学)は、環境や経験によって遺伝子の発現が変化する仕組みを探る学問です。たとえば、幼少期に逆境を経験した人では、ストレス応答に関連する遺伝子の発現が変化しやすいことが分かっています。この変化は、精神疾患や身体疾患のリスクを高める可能性があります。しかし、適切な介入や支援を受けることで、このリスクを低減し、健康的な生活を取り戻すことが可能です。
【安全・つながり・回復の重要性】

NEAR科学では、「安全」「つながり」「回復」の3つの柱が必要だとされています。
・安全:安心感を提供する物理的・心理的な環境の必要性。
・つながり:支え合い、共感を感じられる人間関係の構築の必要性。
・回復(レジリアンス):困難や失敗から立ち直る力を育む支援の必要性。
たとえば、安全な環境では心もリラックスしやすく、家族や友人とのつながりがあれば支えを感じられます。このような安心感があると、ストレスに強い心と脳が育まれます。
NEAR科学の応用例として、以下のような取り組みが効果を上げています:
・トラウマインフォームドケア(※3):トラウマを理解し、それを考慮した支援や教育を行う。
・マインドフルネス:心を穏やかに保ち、ストレスを軽減する瞑想法。
・自然療法:自然とのふれあいを通じて心身の回復を図る。
・体験型学習:自己肯定感を高め、回復力を育む活動。
これらの実践は、個々の支援にとどまらず、教育現場や職場、さらには地域社会全体で広がりつつあります。今後の社会においては、NEAR科学の知見がさらに活用され、より多くの人々が困難を乗り越えられる社会の実現が期待されます。
おわりに
NEAR科学は、ストレスやトラウマが私たちの脳や心にどのような影響を与えるかを解明してくれます。NEAR科学の考え方は、複雑な理論ではなく、小さな「気づき」から始まります。また日常に取り入れやすい小さな工夫で活かせます。例えば、リラックスできる環境作りや、家族や友人とのつながりを大切にすることが挙げられます。また、深呼吸や簡単なマインドフルネスを習慣にすることで、心と体のストレスを和らげられます。これらは子どもから大人まで誰でも実践でき、健康的で豊かな生活をサポートします。まずは「安心できる場所」「支え合える関係」「回復の時間」を意識することから始めましょう。そして、日常の中で自分を大切にする時間を増やし、心身をリセットする習慣を作ることで、より健康で豊かな生活への第一歩になることを願っています。
次回のコラムでは、ストレスが具体的にどのように私たちの身体や行動に影響を及ぼすかを深掘りし、またその回復メカニズムについて詳しくお伝えします。
【NEAR科学】シリーズはこちらからご覧になれます。
【NEAR科学】②ストレスでエンジンがオーバーヒート!? ストレスに強い脳と心をつくるためにできること
【NEAR科学】③日常に取り入れるコツ!対話で育む心と脳の健康
過去の関連記事へのリンクとなります。
※1 ACE:小児期の逆境体験についてはこちらからご覧になれます。
【小児期の逆境体験(ACE)とは・・・】将来の健康のために幼少期のトラウマを防ぐ支援
※2 レジリエンスについてはこちらからご覧になれます。
【逆境にあってもめげることなく頑張れる力】ポジティブな気持ちを育むためにレジリエンスから学べることとは・・・
※3 トラウマインフォームドケアについてはこちらからご覧になれます。
【トラウマインフォームドケアという関わり】①環境要因によって形づくられる子どもの発達の質とは・・・
【トラウマインフォームドケアという関わり】②なぜ今の時代に必要とされているアプローチなのか
【トラウマインフォームドケアという関わり】③子どもの気になる行動の背景を理解するためのヒント
【トラウマインフォームドケアという関わり】④こころのケガになりうる出来事
【トラウマインフォームドケアという関わり】⑤子どものトラウマ反応について
【トラウマインフォームドケアという関わり】⑥トラウマインフォームドケアの原則
【トラウマインフォームドケアという関わり】⑦実践するための4つのR(前編)
【トラウマインフォームドケアという関わり】⑧実践するための4つのR(後編)
【参考資料:『小児期の逆境体験と保護的体験』ジェニファー・ヘイズ=グルード他2名・2022 『子どもの「逆境」を救え』若林巴子・2024】
社会生活の変革という過渡期での不安やストレスは、さまざまな形で表出されることがあります。また、被災地の皆さまにとっては日々変化を遂げる環境の中で、ご心配を抱えた状況の方がいらっしゃることと思います。心身の安全最優先でお過ごしいただければと願います。ポジティブな考えを持つきっかけとして、そして安心・安全な人との関わりを通して生きる力を養うサポートもカウンセリングの一側面とも考えています。子育てやこどもの抱える不安やストレスに関してのご相談もお受けしております。
《お知らせ》
▶オンラインカウンセリング(メンタルトレーニング、コーチング)を導入しております。
どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

▶弊社監修「ユーキャン・心理カウンセリング講座」
受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。
私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!
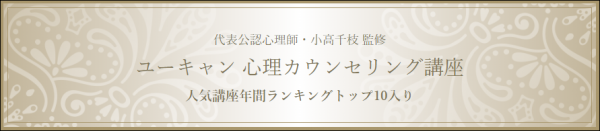
▶弊社監修「ユーキャン・不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」
公認心理師・安澤が監修いたしました!
心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。
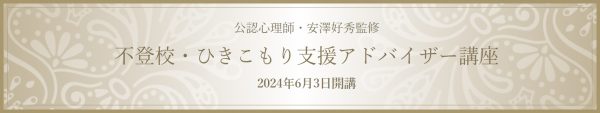
▶『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』
その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません
SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説
2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!