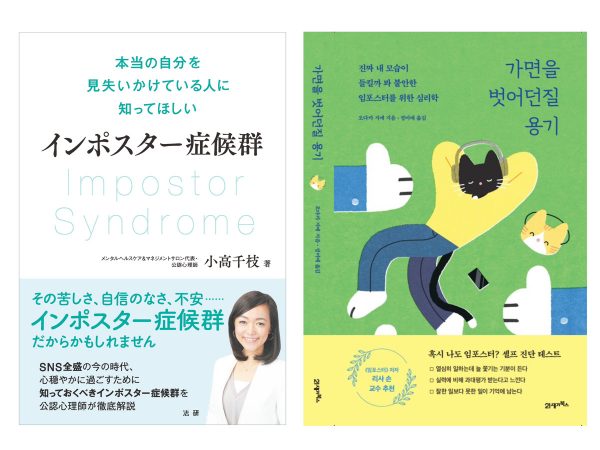所属精神科医のT.Sです。
このコラムでは、
私が精神科医として患者さんと接する中で手に入れ、磨き上げてきた様々な武器
つまりは「幸せになるコツ」
を紹介しています。

つい先日、私は16連勤という無謀なスケジュールからなんとか生還しました…
職場の名誉のために言っておくと、無理に働かされているわけではありません!
訳あって、自ら非常勤の仕事を追加したり当直に入ったり、ということをしているうち、気づいたときには16連勤が組み上がってしまっていたのです。
そして16連勤も終盤に差し掛かった、とある日。
仕事を終えて乗り込んだ電車で気絶したように眠り、頭を全方位から押さえつけられるような感覚に襲われながら、なんとか帰宅しました。
しかし帰宅後も頭はぼーーっとしたままで機能せず、普段は全く気にもせず受け流せるような些細なことでもイライラしてしまいます。
しかも、「あっ、今自分怒ってる!落ち着かないと!」と分かっているのに、それでも止められないのです。まるで、車でアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような感覚。
その時の私は、明らかに心の処理能力、キャパシティをオーバーしていました。
これはまずいなと思い、なんとか態度には出さないよう心がけていたのですが、晩ごはんを数口食べたところ、ふっと冷静になれたのです。そして思い出しました。
ああ、そうだ。自分、空腹になるとイライラしやすいタイプだった…
実はこれ、私にとっては小さな発見でした。「空腹=イライラ」という自分の特性も、キャパシティ管理の一部なんだと改めて感じたからです。
キャパシティとは単に体力や時間の話だけでなく、「どんな条件下でなら自分を穏やかに保てるか」ということでもあるのです。
「コップの中の氷山」
私は精神科医として患者さんと向き合う中で、「キャパシティ」という言葉を多くの場面で意識しています。
そして、患者さん自身が持っている特性とキャパシティの関係を説明するとき、私はよく「コップの中の氷山」の例を用います。

このモデルでは、氷山は “元々自分が持っている嫌な特性” を、コップに溜まった水は “自分の余裕” を表しています。
“余裕” というのは体力であったり、心の余裕であったり、時間的なゆとりであったりします。広い意味での “余裕” だと思ってください。
水がコップになみなみ注がれている状態、つまり ”自分に十分な余裕がある状態” では、自分が持っている嫌な特性も目立ちません。
しかし、水が枯れて干上がってくると——つまり、“自分に余裕がない状態” になると、自分の嫌な特性が顔を出すようになるのです。
患者さんが精神科に受診する時点で、多かれ少なかれキャパオーバーになっているわけですが、単に体力や仕事の量だけではありません。
感情、判断、共感…いわば “心のリソース” 全体の話です。
リソースとは、もともと「資源」「供給源」といった意味を持つ言葉で、物理的には時間やお金、エネルギー、人材などを指します。限りあるものをどうやって配分するか、という観点で使われることが多い概念です。
そして “心のリソース”とは、感情をコントロールする力、他人と関わるエネルギー、物事を考える思考力など、私たちの精神活動を支える “見えない資源” のことです。
人の話を聞いて共感する、複雑な問題を判断する、自分の気持ちを整理する――こうしたことにもそれぞれ心の燃料が必要であり、それは無限ではありません。使えば減り、回復しなければ枯渇してしまうのです。
“心のリソース” が枯渇したことで、溜め込まれ、抑圧されてきたストレス、感情、情報といったものが溢れ返り制御できない状態。
これがキャパオーバーの正体と言ってもよいでしょう。
AIのキャパシティと、その対処法

人間のキャパシティについて考えていたとき、ふと私の頭をよぎったのが、最近何かと話題のAIたち——例えば、対話型AIの代表格・ChatGPTなどのことです。
凄まじいスピードで進化を遂げている彼(彼女?それとも“それ”?)にも、キャパシティというものが存在するのでしょうか?
もしも存在するとしたら、一体どのように対処しているのでしょうか?
結論から言うと、まず彼らも人間同様、立派なキャパシティを持っています。限界がちゃんとあるのです。
たとえば私たちが、勢いよく何百件も質問を一気に送りつけたとしましょう。すると彼らは、いたって冷静に、そしてとても礼儀正しく、こう返してきます。
「ただいま大変混み合っております。しばらく経ってから再度お試しください。」
――なんと的確な対応でしょう。
怒るでもなく、取り乱すでもない。
しかしこれは、AIからの明確な「キャパオーバー」宣言、つまり「もう無理です」のシグナルなのです。
そして素晴らしいのは、彼らがその限界をきちんと“自己申告”してくるところです。
AIは、自分の処理能力を超えそうになると、迷いなく処理を遅延させたり、別のサーバーに仕事を振ったり、果ては処理を止めて断ってくる。いわば「壊れるくらいなら、止まる」勇気を持っている。これはもう、立派な“自己防衛機能”と言えるでしょう。
つまり、AIは「できないときにはやらない」ことがシステムとして許されているわけです。むしろ無理をしないことが、システムの安定運用に繋がる。なんとも合理的ですよね。
自己申告できない人間

さて、一方で我々人間はどうでしょうか。
言うまでもなく人間にだって、キャパシティの限界があります。
日常の様々な出来事により、脳や心に、CPUやメモリのような “負荷” がかかります。
それを無視して走り続ければ、次第にガタが来てしまい、どこかで必ずダウンしてしまうのは当然のことです。
しかし、例えば上司から仕事を頼まれたとき、「今、私は仕事をたくさん抱えております!しばらく経ってから再度依頼してください!」と言える人が、いったいどれほどいるでしょうか。その発言が許される環境が、どれほど存在するでしょうか。
立場上「無理です」と言えない。
「断ったら嫌われるかも…」と気にして引き受けてしまう。
「一度『やります』って言っちゃったし……」と引き下がれなくなる。
そして気がつけば、頭の中ではエラー音が鳴り響いているのに、それでも「まだいける」と自分に言い聞かせ、疲労と不安を抱えながら頑張り続けてしまう。
AIの健康的な働き方が羨ましくなってきますよね…
AIにできて人間にできないこと──それは、「余裕がないときに、余裕がないと認めること。そして、それを伝えること」なのかもしれません。
無理を察知したら止まり、堂々と「今はできません」と言う。これこそ、キャパシティを守る正しい姿勢ですし、長期的に見ると効率も良いはずなのです。
「キャパが狭い」はダメなこと?

「自分ってキャパが狭いなあ……」
そんなふうに、ため息まじりに呟いたことはありませんか?
周囲と同じように動いているつもりなのに、自分だけぐったりしてしまう。
他の人なら全く気にもしないような言葉でも、自分だけ傷ついて引きずってしまう。
そんな日が続くと、つい「自分は劣ってるんじゃないか」と思ってしまうものです。
しかし、実はそうではありません。
「キャパシティが狭い=劣っている」ではなく、そもそも “構造” が違うのです。
たとえば、ある日あなたがカフェに入ったとしましょう。
A店はご夫婦で営む小さなカフェ。席数は少ないけれど、コーヒーを淹れる手つきも、会話の間合いも、すべてが丁寧で温かい。
一方、B店は全国展開しているチェーン店。注文はタブレット、呼び出しは番号制、店員さんはキビキビと動きながらテキパキと大量の注文をさばいていく。
どちらの店にも、良さがあります。でも、「どっちが上か?」なんて議論はナンセンスですよね。そもそも運営の前提も、設計思想も違うのだから。
人間だって、それと同じなのです。
キャパシティが “広い人” は、大量のタスクや情報をさばくのが得意。どんなに人が集まってきても、ある程度までは笑顔で処理してしまえる。でもその分、細かいところが雑になったり、ちょっとした変化に気づきにくかったりもします。
一方で、“狭い人” は、大勢に対応するのは苦手でも、目の前の一人に深く寄り添ったり、小さな変化を敏感に察知したりする力があるかもしれません。
どちらにも向き・不向きがあります。でも、それはあくまで「構造の違い」であって、決して「能力の差」ではありません。
そしてもちろん、今回の対比はあくまでも一例。「キャパシティが広い人=絶対に些細な変化でも気付ける」というわけでもなく、個々人によって程度はバラバラです。
怖いのは、自分がどんなタイプなのかを知らずに、無理に “別タイプ” の動きを真似しようとすること。
この場合、“心のリソース” が早くに枯渇してしまったり、仕事や日常生活でつまづいたりということが増えてしまう恐れがあります。
軽自動車に大型トラックの荷物を載せようとしても載らないのは当たり前のこと。
しかし、大型トラックに小さすぎる荷物だけを積み込んだら、荷台の中で大きく揺れ動いて荷物を壊してしまうかもしれません。
自分のキャパシティについて、その容量だけでなく、性質についても正確に知っておくこと。
それこそが、自分というシステムを守り、長く安定して動き続けるためのコツなのです。
自分のキャパと上手に付き合う、3つのコツ

さて、ここで私自身が日々の暮らしの中で実践している「自分のキャパと上手に付き合う、3つのコツ」をご紹介させてください。
どれも特別なテクニックではありませんが、使いこなせると意外と効きます。
① 自分の“エラーサイン”を見逃さない
人間にも、実はシステムアラートのようなものがあります。
しかし、スマホのように分かりやすく通知センターに出てきてはくれません。自ら拾い上げる必要があるのです。
たとえば、やたらため息が増えてきたとか、冗談を言えなくなってきたとか、同じ話を家族に3回くらいしていたとか。
あるいは、普段そんなに投稿しないのに、突然SNSで「今日のランチ」とか「空の写真」とかを連投していたり…
それ、もしかすると「そろそろ限界ですよ」という心のエラーサインかもしれません。
こうした“地味な不調”は、大きな不調の前兆。ちょっとした違和感を早めにキャッチしてあげることが、キャパ崩壊を防ぐ第一歩になります。
私自身、「頭が抑え込まれるような感覚」を感じた場合はかなり限界が近いサイン。そういうときにはチョコレートや美味しい物を食べたり、その日は早めに寝るように心がけています。これにより、謎の不機嫌や突然の不調がかなり減りました。
② 「やめる」「遅らせる」「頼る」を、あえて戦略に
AIのいいところは、自分の限界を察知すると、潔くこう言うところです。
「今は対応できません。」
しかも、ちっとも申し訳なさそうにしません。
人間も、あれくらい堂々としていいのではないでしょうか?
たとえば、「今日の会議は30分で切り上げよう」「このタスクは来週に回そう」「夕食は冷凍食品で勘弁してもらおう」。
こういう “引き算” を、自分の中で戦略として持っておくのです。
「やめる」「遅らせる」「頼る」は、いずれも心のCPUを守るための “負荷分散” 。
決してサボっているわけではなく、自分のリソースを破綻させないための、立派な自己管理スキルです。
私の場合、連勤が続いて疲れることが目に見えている月には、カレンダーの休日に敢えて「休み!」という予定を書き入れています。
そうすることで、その日は何も予定を入れず、遊びに誘われても断って、しっかりリフレッシュするために使えるように確保しているのです。
③ 自分の “快適ゾーン” を知っておく
どこまでが自分の安全圏で、どこからが危険域なのか。
自分というシステムの “動作環境” を知っておきましょう。これを把握しておくと、日々のパフォーマンスが安定します。
たとえば私の場合は、
・夜は0時までに寝て、朝早起きして犬と散歩すると、一日朗らかに過ごせる
・疲れすぎている日の夜に飲酒すると、翌日さらに調子が悪くなる
・普段は電車通勤のほうが楽だけど、たまに大声で歌いながら車で通勤すると、体の疲れよりも気分のリフレッシュの方が勝つ
こういう「自分がご機嫌でいられる条件」を日常の中から拾い集めておくと、余計なトラブルや無理がぐんと減ります。
これも、キャパに振り回されないための予防策です。
他人のキャパにも想像力を持つ

自分のキャパシティを知ることは、決して「甘え」ではありません。むしろ、自分と他者を理解し、健やかに生きるための “知恵” だと私は思っています。
そう。自分のキャパシティを自覚し、その性質についても深く理解できるようになると、それが他者のキャパシティを考えることにも繋がるのです。
「なんでそんなことで疲れてるの?」
「これくらいのことで怒るなんて大人げない」
こういう言葉、つい口をついて出た経験はありませんか? これは、無意識に「自分のキャパシティ」を他人に当てはめてしまっている状態です。
人によって、感情の処理スピードも、刺激への感受性も違います。大勢と話すと元気が出る人もいれば、3人以上になるともう話せないという人もいる。騒がしい空間で集中できる人もいれば、時計のカチカチ音すら気になって集中できない人もいます。
だからこそ、私たちは「他人も自分と同じキャパだ」と思い込まず、違いを前提にしたコミュニケーションを心がける必要があります。
そして人は、自分がキャパオーバーのときほど、他人のキャパに寛容でいられなくなります。
「私だって我慢してるんだから、あなたも頑張ってよ!」と、心の中の声が強くなってしまいます。
だからこそ、自身のキャパシティを把握して心の余裕を取り戻すことは、人間関係を円滑にするための重要な第一歩でもあるのです。
私たちが忘れがちなこと——それは、「無理しないこと」です。そして、無理しないことは、頑張らないこととは違います。
頑張るために、無理を避ける。
その逆説的なバランス感覚こそ、今の時代に必要なセルフケアなのではないでしょうか。
あなたの“心の使用率”は今、何%くらいですか?
そっと胸に手を当てて、もしもちょっと苦しいなと感じたら、それは「そろそろ休んでいいよ」というサインかもしれません。
どうか、自分の声に耳を傾けてあげてください。
それでは、また次回のコラムで。
※過去のコラムはこちら↓からご覧いただけます。
【メンタルヘルス】精神科医T.Sコラム
Writing by T.S
《お知らせ》
▶オンラインカウンセリング(メンタルトレーニング、コーチング)を導入しております。
どうぞ、ご利用ください。詳細はこちらをご覧ください。

▶弊社監修「ユーキャン・心理カウンセリング講座」
受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。
私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!
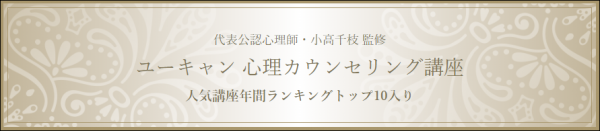
▶弊社監修「ユーキャン・不登校・ひきこもり支援アドバイザー講座」
公認心理師・安澤が監修いたしました!
心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。
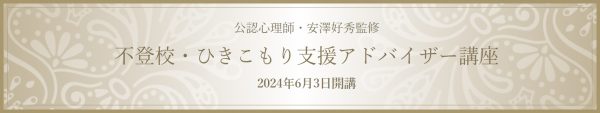
▶『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』
その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません
SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説
2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!