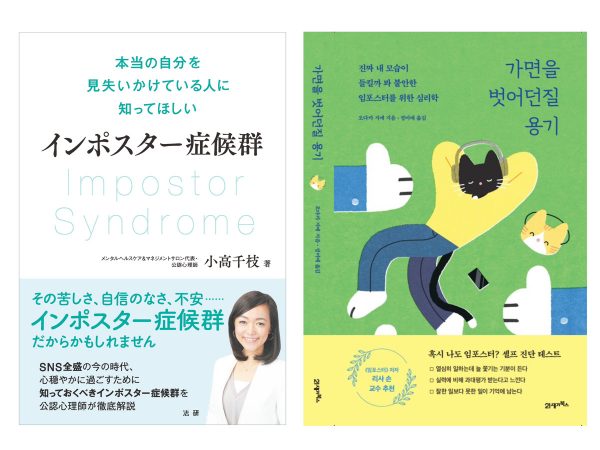皆様、こんにちは
メンタルヘルスケア&マネジメントサロン代表・公認心理師の小高千枝です。
東日本大震災から本日で14年という時間が経過しました。
2011年(平成23年)3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故(放射能汚染)による大規模な地震災害
時代も令和になりましたね。。。

(被災地支援の移動中の車の中より)
毎年、311の記事を書いていますが、忘れられない日であり忘れてはいけない日であり、そしてより前を向くきっかけになる日であり。。。この14年間の経験を財産に武器にしてまいりました。
そして、自分自身の振返りや大切なモノの確認作業の時間としても書かせていただいております。
当時、私は広尾でカウンセリングオフィスを運営していました。
翌日に大阪の番組の初出演を控えていたため、お昼過ぎまでカウンセリングをし、クライエント様を見送った後にひとりで番組準備をオフィスでしておりました。
そして
地震
こんなにも大きな地震の経験ははじめてのため、地震とは思わず「目眩?かな?」と思うくらいどこか他人事でした。
自分の身に、大地震が降りかかるとは思っていないバイアスがかかっていたのだと思います。
キッチンの食器がガタガタ揺れ、玄関の扉が閉まっているのにもかかわらずバンバン音を立てていたことは鮮明に覚えています。
感じたことのない恐怖心に襲われました。
「地震」と自覚をしたのは、それから数分後。
スタッフからの連絡で気付きました。
スタッフも動揺しており、オフィスに電話をしているのにも関わらず「何処にいるんですか???」と。。。
翌日の大阪収録は予定通り。
大袈裟な話ではなく、命からがら何とか大阪にたどり着き、初出演の番組へ挑みました。ただ、気持ちは落ち着かなかったですよね。。。もちろん大阪を満喫する気分にもなれず、収録に全エネルギーを注いでからすぐに東京へ戻りました。(早く戻りたかったです)
楽屋でテレビを眺めながら、現実味をまだ感じることのできないほどの状況の凄まじさに、映画を観ているような感覚に陥り、ただ、どこからかあふれ出る感情を押さえながら、スタジオへ入ったことを覚えています。


(宮城県南三陸町・南三陸ホテル観洋さんが避難所になっておりましたためカウンセリングのブースを設けていただきました)
幸いにも私の周りの人には大きな被害はありませんでした。
母が帰宅困難者になった程度で(なんとか翌日に自宅へ戻ることができました)、家族もスタッフもみんな無事だったことは、本当にありがたいことですね。。。
その後、南三陸での支援活動では現実との向き合いに、自分自身の感情コントロールの壁にぶつかり、災害時のメンタルヘルスは大切ではあるものの、専門家が関わるタイミングの難しさを実感いたしました。


(子どものメンタルヘルス対策としてお邪魔いたしましたが、大人の方にもカウンセリングを受けていただきました)
先日の岩手県大船渡市での山林火災も「どうして。。。」と言葉になりません。。。
やっと鎮火されつつあるようでホッと一安心ではありますが、震災からやっと立ち直ったばかりにも関わらず、どうして?と
東日本大震災での経験をいかした避難所対策もとられていたようです。ただ、14年経過してもまだ足りないことも多々あったとのこと。
私自身、犬を飼っているため被災動物のことはいつも気になります。
ペットの防災対策を考える上でぜひ知っておきたいのは『同行避難』と『同伴避難』の違いです。
▼『同行避難』
災害時に飼い主がペットを連れて一緒に避難することを指します。
避難所でペットと一緒に過ごせるかどうかは、各自治体や避難所の判断に任されています。
▼『同伴避難』
ペットと一緒に避難し、かつ避難所で一緒に過ごすことを指します。
私たち飼い主にとっては、『同伴避難』のほうが理想的ですが、環境省が作成している『災害時におけるペットの救護ガイドライン』で推奨されているのは、『同行避難』のほうです。
環境省・人とペットの災害対策ガイドライン
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/0-full.pdf
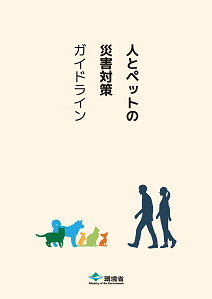
大船渡市での山林火災でもペットの同行避難について問われているニュースも目にすることとなり、大変複雑な気持ちになりましたが
私自身も人間の身の安全とともにペットのさくら(犬・
もちろん、実際に災害に遭った時はとっさの判断が鈍ることもあると思います。用意周到でいても、頭が真っ白になる可能性もあります。何もできなくなったとしても、物理的な環境が少しでも整っていれば。。。メンタル面の安定にも繋がることを意識し、定期的に確認をするようにしています。

(さくらとの避難訓練は日常的。災害時用にリュック型ハウスも購入しました。さくらもハウスのひとつとして捉えています)
また、これだけ災害が多いと「また。。。」「もうやだ。。。」と思ってしまうこともありますよね。
努力を重ねても望む結果が得られない経験が続くと「何をしても無駄だ」と認知が芽生え、不快な状態を乗り越えようとしたり、脱する努力を諦めてしまうことを、学習性無力感(英語:Learned helplessness)と言います。
※「学習性無気力」「学習性無力症」「学習性絶望感」
(ポジティブ心理学 マーティン・セリグマン提唱)
学習性無力感に苛まれましても、私たちは14年かけて向き合ってきた”自分たち”を、”大切な人”を守る知識や経験があります。
そういった自分たちの財産、武器を日常的にもいかし、いざという時にも実際に行動に移していけるように、お互いに声をかけあっていきたいですね。
これからも私たちの日常は続きます。
当たり前の日常が当たり前のように続きますように。。。こうやって健康で生活できていることへの幸せな気持ちを大切に。。。
過去記事として、私のライフスタイルのひとつでもある、ペットとの生活『保護犬・保護猫活動』についての記事も以下へアップいたしましたのでご興味がある方はご覧くださいませ。
【保護犬・保護猫支援活動について】
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)①
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)②
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)③
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)④
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)⑤
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)⑥
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)⑦
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)⑧
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)⑨
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)⑩~ペットは家族。ウクライナにおける生きる権利【1】
▷命あるものとの向き合い(保護犬・保護猫支援活動)⑪~ペットは家族。ウクライナにおける生きる権利【2】
311という日は、大切な人・物・事との生活をみつめるタイミングに私はしておりますので、皆様も何かのタイミングをきっかけに
ご自身の振返りと未来への希望をみつめてみてくださいね。

どうぞ、ご利用ください。
詳細はこちらをご覧ください。


受講生様からの講座内容に関するご質問へ私どもがご回答をしております。
私たちとご一緒に、学びを深めて参りましょう!
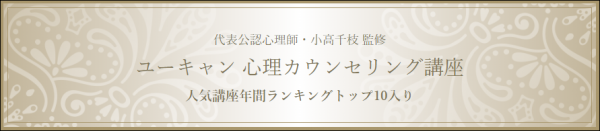

公認心理師・安澤が監修いたしました!
心理学・福祉そしてスクールカウンセラーの観点からお伝えしております。
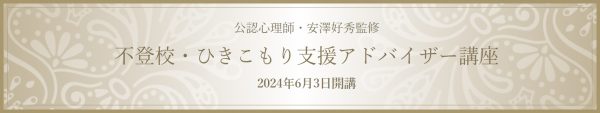

その苦しさ、自信のなさ、不安…インポスター症候群だからかもしれません
SNS全盛の今の時代、心穏やかに過ごすために知っておくべきインポスター症候群を徹底解説
2024年9月に韓国版・出版開始いたしました!
韓国版『本当の自分を見失いかけている人に知ってほしい インポスター症候群』
가면을 벗어던질 용기
진짜 내 모습을 들킬까 봐 불안한 임포스터를 위한 심리학